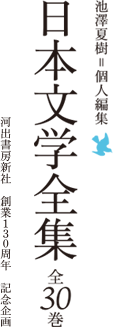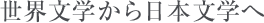
- ――
- 池澤さんの個人編集によって二〇〇七年から刊行され、異例の好評とともに迎えられた「世界文学全集」に続いて、こんどは「日本文学全集」を編まれると発表されました。十一月からほぼ毎月刊行ということですが、まず、なぜ今それを手がけようと思われたのでしょうか。
- 池澤
- 「世界文学全集」が一段落したところで、版元の河出書房新社から日本文学全集もやりませんか、と声をかけていただいた。しかし、そのときにはぼくはやる気はなかったんです。自分はそんなに日本文学に詳しくないし、ともかく世界文学全集が終わった直後だったし。それを言うなら世界文学全集のときも、最初は無理だと思っていましたが。
- ――
- それを翻意された理由はなんだったのでしょう。「世界文学全集」の完結は二〇一一年三月十日、奇しくも東日本大震災の前日でしたが、その後の池澤さんの活動とも関係していますか。
- 池澤
- そうですね。何の偶然か。ぼくはその震災後、東北へ足繁く通うことになりましたが、そのような状況の中で改めて「日本」そのものについて考える機会が増えました。今、「日本」のイメージが揺れているというか、ばらけているというか、以前に比べて大きく変わってきています。3・11以降、今に至るこの間、大きな政治の変動がありました。日本とは何なのか、本来どういう国だったのか、そもそも日本人を名乗る我々とはいったい何者なのかという問いが湧いた。それはぼくだけでなく、世間全体にあった気がします。
- ――
- 第二次世界大戦後の、あるいは従来の政治的スタンスがどうであるかにかかわらず、震災も契機のひとつとして、違う角度で「日本」について考える機会が増えた、ということですか。
- 池澤
- そうです。そんなときに、去年の初めくらいかな、「世界文学全集」をぼくに作らせた河出の当時会長の若森繁男さんがぼくに「やっぱり日本文学全集、やりませんか」ともう一回訊いてくれた。会うまでは「無理です」とお答えするつもりでいたんです。でも話の場に臨んでいるうちに、先に述べた思いもあって、歴史の見直しのような形で日本人像をつかめないか、やってみるだけのことはあるかなと考えなおしました。先の問いに答えることは「歴史」の仕事であると同時に「文学」の仕事でもあるだろう。歴史は時期によって様々な解釈を記していくけれども、文学を通して見れば全体像が見られるのではないか。そういったおぼろな思いがあったんです。
- ――
- 壮大な視野のもとに引き受けることを決めた、と。
- 池澤
- もちろん、大失敗に終わる可能性もあると思いましたよ。なにせぼくは日本のことはあまり知らないから。若いとき、ぼくはこの国とうまくいっていなかった。だから読むものも翻訳ものが多かったし、旅行も国内よりは海外に出るほうが好きだった。でもいつでも「日本」のことが気になっているわけです。自分と相性が悪い、折り合いが悪いと思っていたとしても、だからといって日本人をやめてしまおうと思ったことはない。嫁と姑みたいなものだけれど離縁はしない。
今になってふりかえってみれば、日本の姿をはっきりさせるために他の国を見てまわる、こっちではこんなふうにやっているのかという見聞をたくさん重ねてきたわけです。ギリシアでもフランスでも、短期の旅行に行った各地でも、沖縄に住んでいても。それは外から日本を見ていたということで、日本に対する関心は底流としてあったと思います。

- ――
- そのような来歴の池澤さんにとって、「世界」文学全集と「日本」文学全集、それぞれを編まれる際の大本の基準はどこで共通し、どこが違われますか。
- 池澤
- 「世界文学全集」の場合は時間軸で切りました。基本は一九五〇年以降がメイン、具体的には第二次世界大戦が終わってから9・11までです。「現代の世界を文学はどう説明するのか」という問いかけから編集をした。しかし「日本文学全集」の場合は、我々は何者であるかという問いかけからスタートしています。そのためにはこの列島の始まりから始めたいと思いました。
- ――
- 「空間」ではなく「時間」を軸に全体像を見ようということですね。
- 池澤
- そう。だから『古事記』から始まるわけです。
他の国の文学史と比べていて、ひとつ気づいたのは、日本文学のテーマは、少なくとも近世まではずっと「恋」と「自然」ではないかということ。具体的に他国とどこが違うかというと、「戦争の文学」、「武勲の文学」が少ない。他の国で言えば『イーリアス』や『ローランの歌』の類。
戦記ものといえば、たとえば代表的な作品は日本だと『平家物語』です。でもあれは栄枯盛衰の話であって、戦争の場面もあるけど、それに特化していない。それから武勲でもない。悲劇なんですよ。
なぜそのようになったのか。たぶん、ここが島国で、幸いにも異民族支配を知らずにいられたからではないか。一九四五年まで知らずに住んでいたわけでしょう。
同じ民族同士の戦いは知れています。言葉も同じだし、習慣も同じだし、源氏と平家なんて言ってみればほとんど同類でしょう。古代の皇位をめぐる反乱でも、反乱した当人は殺しても、一族皆殺しまではしていないんですよね。そういう意味ではパシフィスト(平和主義者)である。
日本で本当に大量殺戮が行われるのは戦国時代になってから、それも一向一揆や島原の乱のような宗教がらみの場合ではないですか? あの場合は相手は傭兵ではなかった。異教徒は日本人が初めて知った「他者」であって、異民族のように恐怖を誘ったのかもしれない。
それから、はっきり言って海外での戦争が下手。まず白村江の戦い(六六三年)で負けているでしょう。それから元寇は日本が勝ったわけではない。(豊臣)秀吉も敗退した。勝ったと言えるのは日清戦争だけなんですよ。日露戦争は実際には引き分け。その後はノモンハンでぼろ負け。中国大陸では十五年かけて勝利するに至らず。そして太平洋戦争で徹底的に負けた。
- ――
- そうした意味で、日本の文学は「戦争の文学」ではなかった、ということですね。結果、それ以上に人びとにとって目前の問題であり、かつ本質的に問われるものの一つが「自分たちの前でヴィヴィッドに移り変わっていく四季」、さきほど言われた「自然」だった。では、「恋」についてはいかがですか。
- 池澤
- 日本人の精神にとって色好みはとても重要な要素です。中国文学に恋愛詩はほとんどないんですよ。彼らは自然を詠い、倫理を論じても、恋はほとんど語っていない。
ヨーロッパ文学にロマンスはありましたけど、それだけではない。戦いも陰謀も多かった。インド文学も『マハーバーラタ』なんてずっと神々の戦いの話ですよね。そう考えると、こんなに色恋を語って、四季折々を詠って、それに哀感が漂う。こういう文学史は特異である。
だいたい歴史の長さがすごいです。圧倒的。日本文学史を超えているのは中国だけではないですか。インドは途中で途絶えたし、ヨーロッパはずっと後になって出てきた。日本ではその間ずっと途切れたことがない。
- ――
- その理由は何だったとお考えですか。
- 池澤
- それもたぶん島国だということ。そのおかげで政治が安定していました。乱れてもたいしたことはない。天皇はいるけれども統治はしない。宮中祭祀と色恋を含む文化の継承が主たる任務だった。こんな君主は他の国にはいませんよ。それは日本社会が安定していたからだと思う。争いが下手、争いが嫌いというのは、争いをしなくても済んだということですね。政権の委譲も平和裡におこなわれる。だから言ってみれば、文学をやっている暇があったんですね。それは幸運なことと受け止めるべきだと思います。

- ――
- 全集開始にあたって書かれた「日本文学全集宣言」でも、近代の国民国家形成においては「島国」というシステムがさらによく働いたと書かれていたかと思います。近代の国民国家の前提のひとつは「国境線をどう確定するか」なわけですが、確かに、近代日本は周囲を囲む海がそれを代行した結果、いわば平和な実験場として明治以降の国家像を促成することができた。ところが、二〇世紀末からのグローバリゼーション、あるいはその基盤となるテクノロジーの発達によって、そうした条件が揺らいでいる。かつて「よく働いた」システムが、いまや機能しなくなりつつあると考えていらっしゃいますか。
- 池澤
- そうです。簡単に言えば、飛行機が島を島でなくしてしまった。
- ――
- 飛行機や、ネットワーク越しの情報が「飛び道具」として直撃してくる結果、日本の伝統的な閉鎖性は動揺せざるをえない……近年の右傾化もそういった現実への反動と無縁ではないですよね。その中で池澤夏樹が「日本人とは何であったか」を問おうとする目的は、第一に「かつてから我々は穏やかな文学の民であり、愛と自然の民であった」と示すことに思えますが、そのことは、それがそのまま維持できる、されているという未来への確信や現在への観測と直結するわけではないですよね。
- 池澤
- ええ、違います。とりあえずその点を確認した上で、先のことを考えようという。ここでぼくがまとめてみるからね、ということです。
- ――
- その先のことは自分たちが今から捉える、あるいは池澤さん以降の世代が作ってゆくのだ、ということですね。そうした池澤さんの意識は、大江さんの推薦の言葉の中にもあるとおり、古典を数々の現代作家に新訳してもらう今回のスタイルにも出ているように思います。あくまで個人編集だけれども、単に「池澤夏樹が面白いと思った作品を並べました」ではなくて、それらは現代の作家たちの問題でもあり、さらには読者の問題でもあるのだ、というメッセージではないのかと。そのあたりについても少し伺えますか。
- 池澤
- まず古典については、原文ではなく現代語訳でと思いました。たくさんの人が普通に読むための仕掛けをつくりたかった。もちろん原文でないとわからない深い意味はあります。しかし、日本語ですからね。読む気になったら、世界文学全集と違って、参考書や対訳など支援の装置はいくらでもあるわけですよ。だから入口は現代語訳。
そして翻訳はやっぱり作家の仕事なんです。白状すれば、はじめのうちは先輩たちが残した現代語訳を流用すればいいと思っていた。たとえば『古事記』ならぼくの父、福永武彦がやっています。石川淳さんのもおもしろい。それでいいじゃないかと思っていたら、河出の編集部が勇猛果敢でね(笑)。今の人たちに声をかけてみましょうよ、と言った。
ぼくは、今の作家には日本の古典への関心なんかないのではと思っていたけれど、それならばと思って試してみたんです。そうしたら皆さん、次々に参加してくださった。別にぼくが拝み倒したり脅迫したわけではなくて、河出からの依頼状にぼくの手紙を添えただけでした。こんな風にみなさんがこのプロジェクトに参加して下さったのは嬉しい驚きでした。
- ――
- 二十四人、新釈も含めれば二十八人の人たちが、参加されていますね。
- 池澤
- もしかすると、我々は何者なのかという問いが一種の気運としてぼくらの間にあったのかもしれない。その先で、作家である以上は自分の文体で訳してみたいと思うのでしょう。
ですからこれは文体のサンプル集なんですよ。やり方はそれぞれ違うだろうし、ぼくは手法については、創作にせず翻訳の範囲に収めてください、くらいしか言っていない。そういう最小限の条件からむくむく成立したのがこのラインナップです。
- ――
- メンバーもとても多彩ですよね。高橋源一郎、堀江敏幸、川上弘美、島田雅彦さんたち純文学のベテランから川上未映子、岡田利規、円城塔さんらの若手作家、三浦しをん、森見登美彦さんはじめエンターテインメントの最前線の書き手が並ぶ一方で、詩人の伊藤比呂美、小池昌代さんたち、さらには『負け犬の遠吠え』で知られるエッセイストの酒井順子さんまで、驚くほどに幅広い。とりわけ思想家の内田樹さんの『徒然草』には驚いたのですが、この人選はなぜだったのですか。
- 池澤
- それはみなさん文学者ですから。文体をもっているのは小説家だけではない。
- ――
- 「この人にこれを頼んだら、きっと素晴らしい文章を書いてくれそう」、あるいは「面白いものになりそうだ」という予感で各作品の訳者を決められたんですね。
- 池澤
- そうです。たとえば今回、いちばんの大作である『源氏物語』ですが、角田光代さんに訳していただけることになりました。率直に言って、『源氏物語』はなかなか難しいと思いました。これまでにもいくつも訳があるし、なんたって少なく見積もっても四千枚という大長篇です。かなりの覚悟がいる。
実はぼくは『源氏物語』のあの文体は苦手で、あれほど微妙な心理の綾を丁寧になぞってゆく濃密な文章を読み取る力が足りない。だから誰だったらそれをぼくに読ませてくれるかという気持ちがありました。
ひととおりは知っている。ストーリーはわかっているし、場面も知っているところが多い。でも最初から最後まで夢中になって通読したことは実はないんです。角田さんに声をかけて、たぶんまあ無理だよな、と思っていた。ところが、長い目で見たご自分の作家人生について思うところがおありだったのか、受けてくださった。
- ――
- 角田さんは『曾根崎心中』のすばらしい翻案を先年出されていますし、楽しみですね。一方で、第一回配本で全集のスタートにあたる一巻目は、池澤夏樹『古事記』新訳です。実際に一人の訳者として訳されたとき、どういうアプローチで『古事記』に向き合われたのですか。
- 池澤
- 日本の古典の中でぼくが好きなのは、どちらかというと男性っぽいものなんです。『今昔物語』も好き、『古事記』も好き、『宇治拾遺物語』みたいな説話文学が好き。『平家物語』も好きだったな。どうせ挑戦するならいちばん最初の『古事記』をやろうと思った。
『古事記』は形容詞・形容句の少ない、動詞と名詞の単純な文体なんです。凝った修飾で微妙な空気を描くみたいなことを全然考えていない。誰も彼もまっすぐでぶっきらぼうで、いきなり殺すし、いきなり共寝する。欲望も明快。
福永訳はわかりやすくするために言葉を増やした。説明を本文に組み込んだために冗長になってしまった。もともとぼくの翻訳は言葉を節約するのが特徴で、『星の王子さま』なんかいくつも新訳が出た中でぼくのがいちばん短いと思います。読者には不親切かもしれないけれど原文のリズムと速度感を最重視する。『古事記』もそのつもりでやりました。説明が要るようなことについては脚注を付ける。しかし本文は簡潔に進める。
- ――
- 『古事記』以来の「日本文学」を俯瞰したうえで訳を手がけられるとき、たとえば改行の有無ひとつとってもですが、様々な記述形式や文法の変化あるいは多様性をどこにチューニングするのがベストか、といったことは意識されましたか。
- 池澤
- 改行や主語の補い、字体や句読点など組版のスタイルは大事ですよね。そこはずいぶん工夫しました。『古事記』の場合、難関は固有名詞です。神名と人名。厖大な数が出てくる。古典には作品一つ一つに固有の問題がある。たとえば『源氏物語』は誰の発言かひと目ではわからないんですよ。代名詞が省いてあるから。
- ――
- 当時はたとえば敬語の軽重で見分けがつくようになっていたわけですが、それを敬語表現が貧しくなった現代語で再現するのは非常に難しいですね。
- 池澤
- 今読むと、谷崎訳の「源氏物語」は敬語が煩雑に思える。敬語にこそ日本語の神髄があると彼は考えていたんでしょう。彼自身、私信でも敬語を最大限使っている。松子さんへの恋文のあの敬語ですよ。『古事記』ではぼくはほとんど敬語を捨てました。
- ――
- その意味では、現代の読者たちにとって読みやすい速度に、原文をチューニングされたと受け取ってよいですか。
- 池澤
- そうしたつもりですが果たしてみなさんどう読まれるか。

- ――
- ところで、収録作品を選ぶにあたり、故・丸谷才一さんの文学観を元にしたと記者会見でおっしゃっていましたが、その理由について伺えますか。
- 池澤
- 近代日本文学における明治の中期から昭和三十年代の自然主義小説をどう扱うか、というのが編集方針の大きな課題でした。結局ばっさり切り捨てたのですが。丸谷さんは、あれは横道に入り込んでしまった変な文学だと言っていたんです。それは丸谷さん以前に吉田健一さんの考えでもあります。なぜそういう判断になったかというと、彼らが十九世紀のヨーロッパ文学を学んだことにあります。
十九世紀のヨーロッパ文学は十八世紀から外れて、いやに生真面目な道に入ってしまった。青年が生きる苦悩と正面から向き合うのが文学だというような。日本人はまずそれを学んで、拡大解釈して本家よりも過激に実行した結果、自分に対する誠意だけを書くような求道的な小説が増えた。無頼と求道。それを何とか乗り越えよう、先へ出よう、ヨーロッパでいえば十八世紀までの、笑いの多い、工夫の多い、企みに満ちた文学を日本でもつくろうというのが丸谷さんの小説観で、ぼくもそこに影響を受けています。ラブレーとセルバンテスとジョイスですね、仰ぐべきは。
- ――
- 自分に対する誠実さよりも、ある種の飛躍や実験への試みが重視される部分ということですね。
- 池澤
- そう。「モダニズム」は、古典を重視する一方で非常に斬新な前衛的な実験もする。この両方がなければいけないと彼は言うわけですね。さらにもう一つ、都会的であるというのもあって、この三つがモダニズムの要素であると。
自然主義私小説の人たちは古典なんて読まなかった。本歌取りは自分に対して誠実でないということになるわけです。しかし文学というのは古来ずっと先行作品を踏まえて作られてきました。他人の書いたものを読まないでは自分の作は生まれない。
- ――
- 「近現代作家集」三冊の収録作品が未公表ですが、現在公表されているリストを見ると、明治から現代の作品選択は、いま言われた意味でかなり池澤さん的であるというか、一見偏って見えもします。けれども、いまのお話を伺っていると、古典と直結する豊かなものを選ぼうとした結果だということですね。
- 池澤
- そうです。日本文学でもそれが本来の流れだったのに、西洋に学んだ後で少しぶれたんですよね。文学史としてたどっていくなら志賀直哉もいいけれども、今はそんなに熱心に読まなくてもよいのでは、と思っています。
- ――
- 坪内逍遙から森鷗外、夏目漱石に始まり、自然主義の文学が主流になってゆく時期も含めて、日本の近代文学が主として十九世紀以降のヨーロッパ文学を手本として書かれてきたのは、冒頭の話題にもありましたが、国民国家の形成過程で近代的主体としての「日本人」を構築してゆこうとする政治モデルとも不可分だったはずです。それこそが実は寄り道だったのではないか、と捉えるならば、我々の主体性あるいは人間性も、寄り道を忘れて明治以前に直結してしまったほうがよいと池澤さんは考えていらっしゃるのですか。
- 池澤
- そこまでは言い切れない。しかしこのところ、江戸人は我々の同時代人という認識があるでしょう。あれだけ遊びに遊んで、言葉でも絵でも芝居でも遊んでね。その後で禁欲主義的になってきたわけですよ。それは富国強兵とつながっているのかもしれない。笑いを忘れて。
インテリたちが書いた自然主義小説ではともかく皆悩む。職業のことが話題にならない。人というのは社会的な動物ですから、他人とのネットワークの中で生きているし、職も大事でしょう。それが正面に出てこない。
職業を詳しく書いたのはプロレタリア文学ですが、しかしこれは逆に職業しか書いていない。そういう時代を経て、ようやく少し愉快なものが書けるようになった。芥川賞の選考委員をやっていて思ったのですが、ここ十年ほどでずいぶん雰囲気が変わりました。みんな素材にも文体にも構成にもとても工夫を凝らすようになった。日常生活リアリズムが少なくなった。
ある時期のある種の文学は笑いがなさすぎた。それから、翻訳も含めて先行作品に対して開けたところがない。そういう教養主義はインテリのお遊びだから社会や自分と対峙していないということになっていた。それはやっぱり文学本来のありようではない。
……というふうなことを、ぼくは丸谷さんを読みながら、あるいはご本人とお付き合いしながら、納得していった。丸谷さんに救われたわけですよね。自分の文学観がそんなに間違っていなかったということで。
もし丸谷さんとぼくで一つ文学観が違うところがあるとすれば、さっきの「モダニズムは都会的である」という点です。それを認めた上で、しかし一方でぼくは中上健次も石牟礼道子も宮沢賢治も、つまり日本の地方に暮らしてそこを書いた作家をも重視したい。
- ――
- その三人は、池澤さんの基準では「モダニズムの書き手」になりますか。
- 池澤
- 宮沢賢治はそうですね。あのいたずらぶり、工夫。モダニズムですよ。ぜったいに素朴ではない。石牟礼さんもあの技術、様々な文体を駆使して構築した作品群は確かにそうです。中上だって自然主義からはるか遠いところにいる。自分には悩んでいない。

――
国民国家としての近代日本が、標準語や教育制度に代表されるように、全国を東京的に画一化しようとしていく。その過程で、それぞれの地方で、無関心に背を向けるのでもなく、しかし決して取り込まれもせず、絶妙なバランスの闘いを挑んだのが、さきほど名前を挙げられた三人であるのだと思います。そのうち、中上健次の巻では、数多ある作品から『鳳仙花』を軸に、『千年の愉楽』などの連作からいくつかを選ばれていますね。彼のように多作な小説家の作品の取捨選択は、どのような基準で行われたのですか。ことにいわゆる「秋幸サーガ」の中心作である『枯木灘』ではなく、その母の物語である『鳳仙花』を選ばれたのは、なぜなのでしょう。
池澤
これは他についても言えますが、今回ぼくが一人で編集している以上は、編集の妙を見せたい。ひとりの優れた作家には多様な面があるわけだから、それが見えるようにしたいというのが基本方針で、一巻の中でどう作品を選んで配置するかをとても考えました。昔の文学全集というのは、いかにも代表作といった長篇を一本ぽんと入れて、あとはページ数を合わせているだけという、実に大雑把ないいかげんなセレクションをしていました。でもそれでは面白くない。
『鳳仙花』を選んだのは、『枯木灘』などに比べてぐんとうまくなったのが『鳳仙花』だったから。だからあれを中心に据え、更に彼の全容がわかるように他のものを細かく選んで配置していく。そして全体としてあるまとまりが出るように調整しました。
――
技量を重視しながら、中上健次という作家像が浮かんでくるように、ということと捉えてよいでしょうか。たしかに『鳳仙花』は、分量的には『枯木灘』と『地の果て至上の時』の中間ですが、描かれている時代がかなり長くて、それ自体壮大なサーガになっていると思います。その意味で、さきほど池澤さんが言われた観点でも、一つひとつの内面に向き合って書いていく以上に、大きなロマンを語るということを始めた作品ですよね。
池澤
それはぼくの好みかもしれない。だけど一個一個の事件については拾うかたちで、長篇は時にはばらしてチャプターを一つ二つもらってくるというかたちもできたわけです。オリュウノオバの嘆きについては『千年の愉楽』を一部分収録すればうまく組み込める。
――
そのような視点が、中上健次以外の巻にもそれぞれ、先ほど編集の妙と言われたものとしてこめられているんですね。
池澤
そう。大岡昇平さんも『武蔵野夫人』の他、『俘虜記』から「捉まるまで」を選ぶなど、細かく配置しました。
大江さんは難しかったです、ひとつひとつの作品が長いので。もしも本当に大江健三郎を代表する一作といったら、ぼくは『同時代ゲーム』です。でもそうすると他のものが入らなくなってしまう。全集の編集にはそういう現実的な問題もあります。
『人生の親戚』がぼくは好きなんです。長さがちょうどいいこともあるけれど、まり恵さんというヒロインが魅力的です。それから、作者とストーリーの位置関係がうまくいっている。それからもう一つは『治療塔』を入れる。この二つにあるのは何かというと「女性原理」で、ぼくはある時期から後の大江さんをこう見せたかった。
――
「堀辰雄/福永武彦/中村真一郎」で一巻が立っていることも印象的です。そうした人選の組み合わせには、どんな意図がありますか。
池澤
堀辰雄は『かげろうの日記』、あの二部作ですね。彼がフランス文学に学んだ系統ではなく、日本の古典とのつながりを重視したかった。そちらのほうを強調しようと思った。
福永の場合もこの方針に沿えば『風のかたみ』という、『今昔物語』を下敷きにしたエンターテインメントを採ることになるがこれがまた長い。そこで初期の中短篇を集めることにしました。
中村さんは間違いなく『雲のゆき来』がいちばんいい。絶対に誰が何と言おうと、これがいちばん。これは丸谷さんとぼくの意見が一致しているところだった。これも半分は江戸初期の元政という男の話ですから、日本の古典への目配りが十分にある。それで国際的に名の知れた混血の女優が出てきて、西洋的なものもある。うまくできた話です。
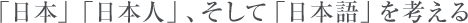
- ――
- ここまでのお話を踏まえると、全集のどの巻にも、池澤さんの目配りとバランス意識が込められていることがよくわかります。その意味では、ごく個人的なものでありながら、同時にとても批評的であろうともされている。そうした意識の中で、選書自体としてとりわけ実験的で挑発的なのが、最後の三十巻ではないでしょうか。
- 池澤
- 「日本語のために」の巻ですね。これが日本文学を担ってきたこの言語は何なのだというところでさまざまな実例や論を集めるつもりです。翻訳について言えば、たとえば聖書マタイ伝の翻訳を何種類か並べてみる。キリシタン版から文語訳、口語の新共同訳、個人のものとしてバルバロ訳、さらには山浦玄嗣のケセン語訳、そういったものを並べて、翻訳を通じての文体論を試みる。
- ――
- 「日本国憲法前文」も収録されていますね。
- 池澤
- あれは名文なんです。ぼくの新訳を入れるかもしれません。対比として、「大日本帝国憲法」もどこか一部分をいれましょうかね。
「大日本帝国憲法は格調があって名文である。それに比べて、今の憲法は悪文である」ということを言い張る方もいますよね。たしかに大日本帝国憲法は格調が高い。しかしその分だけ内容が曖昧なんですよ。つまり文体負けしている。そういうところの違いを並べて見せたい。
- ――
- その着地点を踏まえて考えると、池澤さんにとって、この全集の読者像というものはあるのでしょうか。
- 池澤
- ぼくはあまり読者像を想定しません。とにかくどこか何かのタイミングで本と出合って読んでもらえればいいとしか思っていないから。もちろんこれは日本文学全集ですから日本国内で広く読まれるでしょうし、ひょっとしたら現代語訳は読みやすいから、海外でこれから訳してみようという試みも出てくるかもしれませんが。
- ――
- たとえば角田光代訳の『源氏物語』が、英語などに重訳されるということですね。
- 池澤
- その場合、重訳はいけないとは言い切れないでしょう。素人の読者たちはリーダブルなテキストで物語を楽しんでいいはずなんです。そうでなければ現代語訳自体に意味がない。そういうふうな扱われ方をしたら、それも愉快であるなと思いますよ。
- ――
- つまり、決して「カノンをつくろう」と思っているわけではない、ということでしょうか。
- 池澤
- ええ。世界文学のときもカノンだとは思っていなかった。カノンだとしても、ぼくの勝手なカノンです。何の権威もない。今回もそうですよ。他をさしおいてこれを読んでくれとは思いません。同じような企画を他の方がしたら、それも面白いでしょう。それでも一度こうやってまとめて束ねてみると、全体像が見えやすくなる。まずはこれだけ見ればいいんだという拠り所ができるでしょう。それを提供したい。
- ――
- 全体像ということは、途中のお話でもあったとおり、いずれ完結したときに「池澤夏樹にとって日本とは何か」が見えてくるのだと思います。それは、近代と過去を好き好きに接続して「このようなものが日本である」と信じている人たちのそれと違うのはもちろん、近代国家としての日本や戦後民主主義下で前提されている「日本」像とも、まったく違うものになるのかもしれませんね。
- 池澤
- でしょうね。ぼくも作業を進めている最中なので、まだはっきりとはわかっていないけれども、三十巻を並べて、そうか、こういう姿だったのか、とわかると楽しいと思います。
- ――
- 冒頭のお話にもあったとおり、震災や国際情況あるいは経済情況などさまざまな理由から「日本」像について揺らぎが感じられるなか、日本に限らず、極右的な発言や排外的な振る舞いが目に余りもします。ぼく個人はそれらをまったく肯定できませんが、ただ単に否定するだけでも、対立するだけで膠着してしまう。一人ひとりの個人の内面でも同じことで、たとえば戦後日本が持っていた「日本」に対する複雑な距離感、いわゆる愛国的なものへの嫌悪感や日本的なものに対する拒絶感も、感覚的なものだけで維持できると考えるのは思考停止という意味で同じことだとも思います。結局のところ、単一の国家観や国民像が無条件に共有可能だと信じること自体が暴力的なわけで、国家をめぐる議論はつねに「私はこれをこの国と信じる」という主張と、「自分と違う国家観を押しつけないでほしい」という反発、コインの裏表に見えるけれども実は異質な二つの感情がない交ぜになってしまうことが、問題の根源にあるのではないでしょうか。
そんななかで、今日のお話を伺って、この「日本文学全集」があらためて貴重に思えるのは、たとえば「日本」と呼ばれているものも「唯一無二の日本」ではなく、そこに生きるそれぞれの人間にとっての個別の「日本」像がありうることを、「個人編集」の「日本文学全集」という、どこか語義矛盾を孕みすらする企画自体が肯定して感じられる点です。そこで言われているのは「これが日本だ」といった尊大さではなく、「これが文学者・池澤夏樹にとっての日本です」であり、そうである以上「あなたにとっての日本」も肯定されているわけで、それらはまったく統一のものでなくていいんだよ、というメッセージを可視化することが、なにより素晴らしいことではないでしょうか。
- 池澤
- おっしゃるとおりです。それぞれの読者が「日本」、そして日本文学がそれぞれの人間によってどう違うかを論じるのは面白いし、その議論のきっかけになればとは思っています。