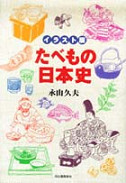検索結果
[ 著者:永山 久夫 ]の検索結果
-
クリやイノシシの肉で作った縄文クッキー、戦国武士の出陣食、江戸時代から人気のすしなど、日本人が愛してやまない食の変遷史1万余年を解き明かす、食文化史の第一人者による決定版。
-
食文化史の第一人者が、“うんちく”を傾けた待望の書。酒造り日本史、江戸の酒と肴、酒に関する風俗習慣、日本史上の酒飲みエピソード、酒肴の雑学など、面白くてためになる話が満載。
-
煮炊き用の土器を使用して革命的食事システムを築いた縄文時代、天ぷら・鮨・スキヤキという国際食を生み出した江戸時代等々、日本列島に展開された食の文化史をイラスト中心にまとめる。
-
サルからヒトへの何百万年にもわたる進化の過程は、食生活の高度化の追求の歴史だ。自然のままを食べた時代から土器の発明による本格料理の時代の食生活を、豊富な資料を駆使し、興味深く解き明かす。
-
そば、天ぷら、鮨、納豆、豆腐――。日本を代表するたべものは、ほとんど江戸時代に出揃っている。どのような土壌の中から、江戸食文化の創造性が出現したのかを、豊富なエピソードをまじえ解明する。
-
秀吉・家康が天下を取った秘訣は食にあった。玄米・大豆・胡麻・魚・野菜をベースにした食事は、体力・知力を高めるだけではなく、強運をも呼び込んだ。数多くのエピソードから、生き抜くヒントをさぐる。
-
当時の平均寿命(30歳台)を考えると、戦国武将は意外と長生きだった人が多い。本書は、なぜ彼らが一般人の二倍近くも長生きできたのかを食生活の面から探り、現代人に食事の改善を提言する。
-
“どんぶり物”は“突っけんどん”がルーツ、“トマト”はかって媚薬だった、“花見”は古代人の花粉健康法など、日本の食のはじまりを、隠し味の面白話をまじえて、料理法から語源まで徹底的に探求する。
-
酒と同様、肴にも長い歴史があります。本書は、干し貝、ハチの子など縄文人の山海の珍味にはじまる日本列島の酒の肴の数々を、豊富なエピソードをまじえて解説し、読者に“読む肴”を提供します。
-
食ことわざ百科
- 定価
- 534円(本体:485円)
- ISBN
- 978-4-309-47082-5
- 在庫
- ×品切・重版未定
- 発売日
- 1985.10.04
梅はその日の難のがれ、大根どきの医者いらず、仕方なしの米のめしなど、日本人が生活の中で身につけてきた知恵の言葉を、食文化の研究家である著者が、独自の観点から選び出し、解き明かします。
-