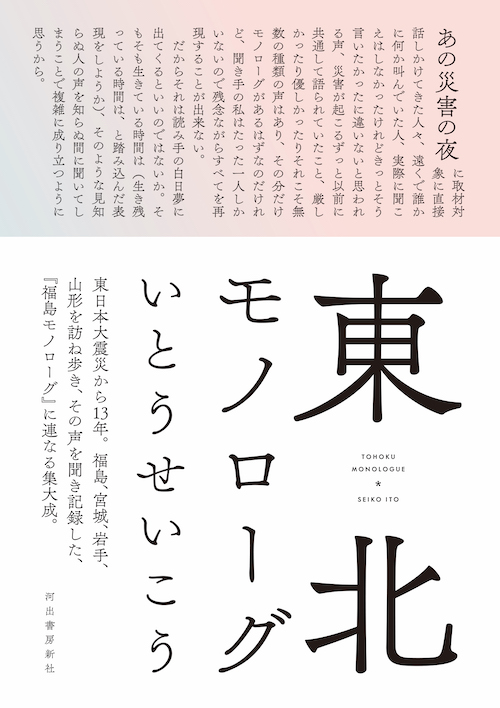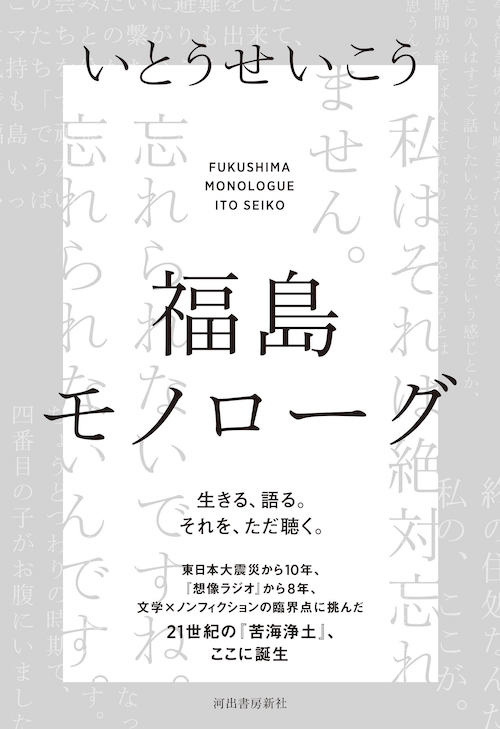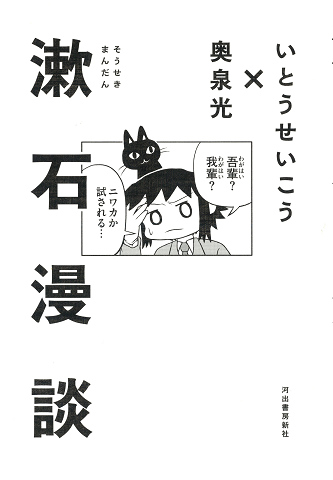- ジャンル:
河出文庫 ● 216ページ
ISBN:978-4-309-40918-4 ● Cコード:0193
発売日:2008.08.06
定価627円(本体570円)
△3週間~
-
小学生の間でブームとなっているゲームソフト「ライフキング」。ある日、そのソフトを巡る不思議な噂が子供たちの情報網を流れ始めた。八八年に発表されベストセラーとなった、いとうせいこうデビュー作。
*下記は、1991年5月に刊行された新潮文庫版『ノーライフキング』に収録された解説原稿です。
執筆者の「岡田幸四郎」さんは作家・重松清さんの別名義です。
解説
岡田幸四郎
子供は、やがて死ぬ。子供でいられなくなる。永遠の子供などはいない。誰もが、生まれてから何年かを子供としてすごし、あるラインを踏み越えることによって、子供という呼称と、そう呼ばれていた自分自身とに決別する。それを"死"と呼ぶか"成長"と呼ぶかはともかくとして、終わることを宿命づけられた存在、それが子供なのだ。
女の子の場合なら、ことは簡単だろう。初潮というはっきりとした微(しるし)とともに、彼女は子供時代を終える。体内から流れ落ちつ一条の赤い血は、子供の"死"を告げる儀式を彩るには、これ以上ない鮮やかさを持っている。
問題は、男の子だ。第二次性徴そのものが女の子よりも進行が遅く、かつ女の子の流す経血に対抗しうる鮮明な徴を持たない男の子たち。彼らは、自らの"死"をどう認識し、どう立ち向かおうとしているのだろうか。
その答えは、本書にある。
いとうせいこうは単行本版のあとがきで、シノプシス作成二時間、執筆二十日間という創作に要した時間を明記している。むろん、彼は、執筆の速さを誇っているのではない。むしろ逆だ。一刻も早く語らなければならないという強迫観念にも似た思い出、彼は無機の王の物語を封じ込めたはずだ。
間に合わないーー。
その思いは、作品を貫いている。
まことがテストの合間を縫って洋太にメッセージを送る描写を思い浮かべてもいい。子供たちの理解者であろうとした大人・水田とまことが、閉まりかけたエレベーターにまことが飛び乗ることで決別したシーンでもいい。《まことに残された時間はかぎられていた》というフレーズは、作品全体に敷延されている。子供たちは、皆、残り少ない時間の中でもがいているのだ。
"王"と呼ばれるものは、すべて、時間を統合する。王の死によって時代に線が引かれる元号問題や、王が季節や人民の生業を司る祭祀などの例を挙げるまでもないだろう。絶対的権力者の"王"は、人民の生死を支配する。これを人民の側から見れば、つまり、彼らは生きる時間を支配されていることになる。
それは古代・中世にかぎらない。J・アタリが『時間の歴史』の中で述べているように、近代社会の特徴でもある大量生産の嚆矢となったのは、ほかでもないゼンマイ仕掛けの時計だったのだから。あるいは、イギリスが、グリニッジ標準時にいまなお往時の栄光を象徴させているように。
人々は時間の中に組み込まれている。その時間は、二十四時間制度に還元される場合もあれば、そうでない、もっと強い呪縛を持ったものの場合もある。子供たちを支配する時間は、後者だ。子供たちは、循環しつづける二十四時間制度の中で生きているのではない。死ぬことを宿命づけられた彼らの時間は、むしろ、砂時計の刻むそれに近いだろう。
となれば、本書の冒頭部分に提出された、あすなろ会への道順や所要時間の記述も、別の意味を帯びてくる。《逆転の発想》と表現される、まことの辿る複雑な道順は、時間による位置関係と空間による位置関係とのずれの現れだとは言えないだろうか。
子供たちのネットワークもそうだ。彼らは、学校や塾といった地域的なつながりを超えた交友関係を結び、電話やパソコンを使ってリアルタイムにアクセスする。数字の配列にすぎない電話番号は、たとえば3を4と押し間違えただけで、地理的にはなんの関連もない家につながってしまう。住所の番地を間違えるのとは、根本的に異なっているのだ。
だから、まことは地理が苦手である。《福島県の県庁所在地》など、彼には必要ない。電話線によって、あらゆる対象への距離は等価になる。つまり、ここでは、距離と時間という比例関係が成立しないことになるのだ。電話を使った新しいメディア、ダイヤルQ2への大人たちの批判の矛先が、時間と距離とに比例するアクセス料金へ向けられていることは、その点で象徴的だ。大人たちは、金という卑小なレベルで、子供たちの持つ歪んだ(けれどきわめて魅力的な)時間を自分たちの側に強引に引き寄せようとしているのだ。
しかし、子供たちの時間は、彼らが"死"を迎える存在である以上、やがて大人たちの時間へと組み込まれていくことになる。それを知り、なおかつそれに抗おうとした子供たちは、どんな手を使うか。
ここで、子供たちの噂が登場する。
一九八六年から一九八七年にかけてマスコミ(つまり大人たちの世界だ)を賑わせた子供たちの噂の代表的なものを二つ挙げておこう。まず一つは、『ドラえもん』ののび太は植物人間であって、ストーリーはすべて彼が見ている夢の世界でのことなのだ、というもの。もう一つは『サザエさん』の一家が悲惨な別離を迎える、というもの。この二つの噂には、”死”のイメージもふんだんにちりばめられているが、それ以上に、時間に対する強い意識が漂っている。子供たちは、植物人間という成長でも死でもない時間の流れ方(死にながら生きる=ノーライフ!)を発見した。そして、時間が先に進まない円環の構図を持つ『サザエさん』を拒否した。"死"に向かって進まざるをえない子供たちは、永遠に小学生でいられるカツオを、ある面で許しがたい存在だと見なしたのではないだろうか。
寄り道がすぎたかもしれない。だが、いとうせいこうは、本書で、登場する子供たちそれぞれの"死"の迎え方を描いた。それは確かだ。物語の中盤に置かれた、みのちんの《シニベタ》の祖父の疑似葬儀のシーンは、この物語全編を通して最も美しく、最も哀しい。セレモニーに臨む子供たちが、皆、自分自身の中の子供の"死"を予感しているからだ。みのちんが祖父に語る言葉、《おじいちゃんの部屋は閉めておいて、たまに開けようと思います。懐かしくなったら開けて匂いをかぎます》は、子供たちが自分自身の物語を封じこめようとした《賢者の石》に重なり合う。《忘れないで》のメッセージも、同様に。
さて、本書は、まことの"死"の迎え方と抗い方を軸に語られる。彼は、懸命に"死"と戦おうとする。"死"の先で待ちかまえる大人たちに立ち向かおうとする。
彼は、《暗黒迷宮》の中に、赤く輝くライフキングとなって飛び込んでいく。暗黒と赤。これは、ゲームのつくるコントラストだけではない。《黒い画面の中央に赤い文字がにじみ出てきた。/「LIFE KING」/それはシンプルだが力強く美しかった》という構図は、作品全体の中でも有効なのだ。この物語には、色彩の描写だけが奇妙なほど突出している。それを辿ってみればいい。
《赤いトレーナー》《真紅のスタジアム・ジャンパー》《厚手の赤いコート》……まことが着ている服は、記述があるものについてはすべて、赤い色をしている。それに対して大人たちの服は、たとえば《ファッツ》の校長は《えび茶色のスーツ》、水田は《薄茶色のコート》。これは服装ではないが、いじめっこの望月の母親の似顔絵も、《脂ぎって黒ずんだ顔に似合わない赤茶けたメガネのフレーム》……。注意深く読み返してみると、作品中に現れる色の大部分が赤と黒の中間の茶系統であることに気づくはずだ。大人たちは、もはや《暗黒迷宮》に溶け込んでしまいつつある。物語の主要な舞台である小学校の校名まで、《黒見山》なのだから。
だからこそ、水田との訣別に先立って語られる次のようなシーンが、重みを持ってくる。《水田は短くなった煙草を投げ捨てて、静かに立ち上がった。柵にからみついていた赤黒い錆が、こげたアップルパイの皮のように何枚も崩れ落ちた。その向こう、冷たく湿ったアスファルトの上で、風に吹かれ、不規則な呼吸を続けている小さな溶岩を、まことは見つめた》。水田は、戦士の証である赤い色を捨てた。まことは、彼が捨てた煙草の赤をじっと見つめる。二人の訣別は、そこですでに予感されているのである。
暗黒の世界に立ち向かう赤い戦士・まことの姿は凛々しく、美しい。
さらに、もう一人。これも美しい戦士がいる。自分の分析表をつくることによって《暗黒迷宮》から脱出しようとする、さとるだ。
自分の分析表ーー。ここで、想起せざるを得ない哲学者がいる。J・P・サルトル。"自分が、いま、ここにある"ということを求めて自分を徹底的に微分しつづけ、分析不能の(つまり百パーセントにならない)部分こそが自由なのだと見なしたサルトルの思想は、さとるの戦いに通じるのではないだろうか。サルトルとさとる。むろん、勝手なこじつけにすぎないかもしれないが、この二つの名前は、あまりにも酷似している……。
いとうせいこうは、本書にかぎらず、『難解な絵本』でも『ワールズ・エンド・ガーデン』でも"自分とはなにか"を語る言葉を探そうとしている。それも、子供たちや、都市につくられた期限つきの砂漠(デゼール)など、常に週末を意識せざるをえない設定のもとでだ。民話の多くが、老人と子供という"死"を迎える存在を中心に据えるのと同じだ。
だが、まことは、ほんとうに自分の物語を《賢者の石》に封じこめたのだろうか。答えは、わからない。みのちんの《ジバク》が、自爆なのか自縛なのかがわからないように。
永劫回帰(これも時間の流れへのアプローチだ)を唱えたニーチェは、《ツァラトゥストラかく語りき》の中で、「小児は無垢である。忘却である」と言っている。つまり、厳密には、子供たちは自分の過去についての物語をつくれない存在なのだ。とすれば、子供たちは自分の物語を封じこめることで、死んでしまったのかもしれない。《忘れないで》と訴えることで、自身の内なる子供と訣別したのかもしれない。
いとうせいこうは、そこについてはなにも語らない。彼は、あとがきでも書いているように、子供たちを"終わらせなかった"のだ。『千夜一夜物語』が美女の延命策として語られたことを思い出そうか。物語は、常に、なにかの終わりを繰り延べるために語られるものなのかもしれない。
本書の読者である大人は、戦う子供たちがやがて"終わってしまう"ことを知っている。だからこそ、無機の王の物語は美しい。本書は、我々自身の《賢者の石》でもあるのだ。いとうせいこうが、あえて空白のまま残した部分になにを打ち込んでいくか。それは、我々がどう戦ってきたかにかかっているだろう。
たとえば、あなたの内なる子供は。
どんなふうに死んでいったのだろうかーー。
(1991年3月)
著者
いとう せいこう (イトウ セイコウ)
1961年生まれ。出版社の編集者を経て、音楽や舞台、テレビなどでも活躍。88年『ノーライフキング』でデビュー。99年『ボタニカル・ライフ』で講談社エッセイ賞、13年『想像ラジオ』で野間文芸新人賞受賞。
この本の感想をお寄せください
本書をお読みになったご意見・ご感想などをお気軽にお寄せください。
投稿された内容は、弊社ホームページや新聞・雑誌広告などに掲載させていただくことがございます。
※は必須項目です。恐縮ですが、必ずご記入をお願いいたします。
※こちらにお送り頂いたご質問やご要望などに関しましては、お返事することができません。
あしからず、ご了承ください。お問い合わせは、こちらへ