読者の声 最新一覧
ご投稿いただいた最新の読者の声をご紹介しています。
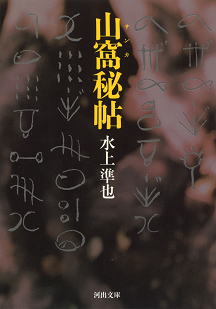
山窩秘帖
水上 準也 著
★2017.05.06 なかなか面白かったです、名前はある作家のようですが、忘れられていたのですね。私は数年前まで豊橋の大学に勤務していたので、懐かしい地名が沢山ありました。この山は石巻山ですかね。
今は住宅地ですね。修羅乙女が原題ですか?
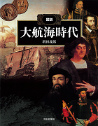
図説 大航海時代
増田 義郎 著
★2017.05.01 最近、横浜市の図書館にてこの本に出会いました。コロンブスがアメリカ大陸を発見する以前から、15世紀にこれほど活発に大航海が行われていたことに未知であったことに恥じ入るばかりです。貴重な資料が沢山挿入されており、増田先生の編纂によるこの書物を大変興味深く読み、「ポルトガルの歴史」とともに、保存版として、購入したいと考えております。ありがとうございました。
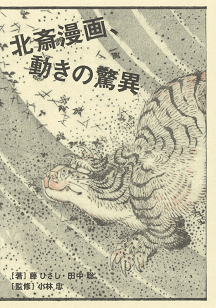
北斎漫画、動きの驚異
藤 ひさし/田中 聡 著 小林 忠 監修
★2017.04.26 本書は、北斎画がまさに「動き、音、におい、その他周辺の環境状態」をも発していることを示していました。
だいぶ前ですが上野の国立博物館における北斎展で、北斎の「部品図」に遭遇して、その天才に愕然としたことを思い出しました。絵が瞬間を切り取っていました。
本書はその時の衝撃の一因を私に示してくれました。北斎漫画のすべてを見せていただけるような書籍の発刊を期待します。贅沢な希望ですが・・・。
著者の皆様と御社に心よりの敬意を表します。

5分後に戦慄のラスト
エブリスタ 編
★2017.04.26 5分で読める、ということで通勤のおともに購入させて頂きました。
どの作品も面白く、結局家でも読んでしまい、ただいま読み終えたところです。特に「見知らぬ同窓会」という作品が不思議な雰囲気のなかで実際に起こりそうな物語でもあり、興味深く読ませていただきました。
ほかのシリーズも手に取ってみたいと思いました。
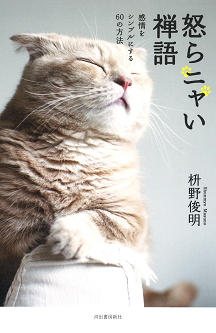
怒らニャい禅語
枡野 俊明 著
★2017.04.25 宗教、禅、論語、コヴィー、、、、
つながってる気がする。
人間なんてそんな変わるものではない。
いろいろ悩んで、そこから得たことを言葉に、文章にして、
他の人に伝えて、こうやって残る。
そんな大層なことをしているわけでも言っているわけでもない。
ごく普通に、自然に考える。
心を整える。
それがなかなかできないから、人はそういう言葉を求める。
私もいろいろ考えて、ある程度心を整えることができたつもりになっている。
でも新たな難題が降りかかってくると、またバタバタする。
その繰り返し。
そういうときに、こうした言葉を読む。
わかっていることだけど、文字で読むと落ち着く。
もう一回自分のものにする。
その繰り返し。
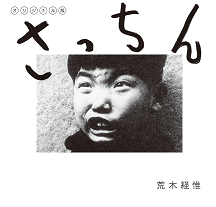
さっちん
荒木 経惟 著
★2017.04.24 写真集を見て思わず笑ってしまったのは初めてだった。
どうしてだか、ずっと印象に残っている。
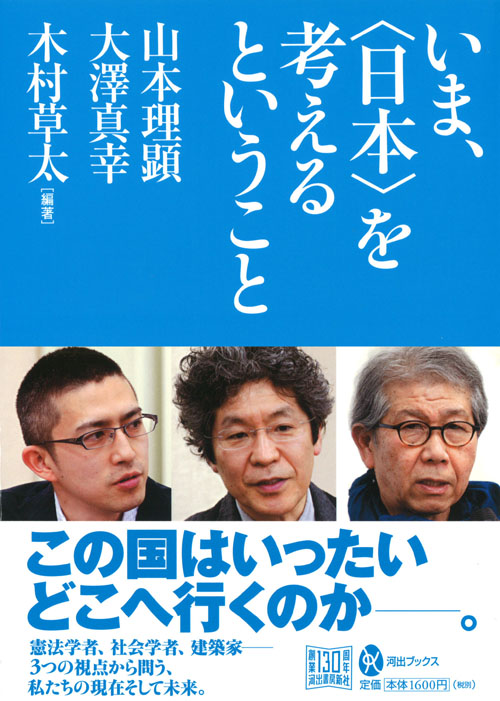
いま、〈日本〉を考えるということ
木村 草太 編 山本 理顕/大澤 真幸 著
★2017.04.21 木村草太先生が、山本理顕先生と大澤真幸先生への愛を元に、企画・実行した探求の記録。すばらしい。大澤先生の核心部分を木村先生がわかりやすく抽出しているのも、この本の余得。
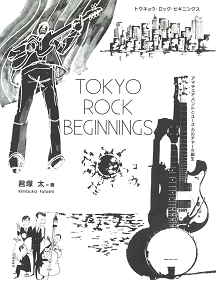
TOKYO ROCK BEGINNINGS
君塚 太 著
★2017.04.20 大変、興味深く読ませていただきました。ここまで的確に人選され一堂に会して証言をまとめられたことに驚嘆しました。本書の結論である「細野さんと早熟な高校生」と題して続編が編まれることを期待します。
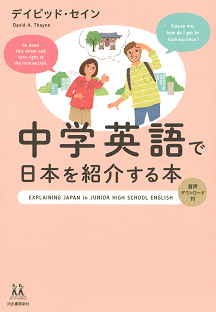
中学英語で日本を紹介する本
デイビッド・セイン 著
★2017.04.16 6月にオーストラリアから3名家族が滞在します。おもてなしの機会到来です。
が、
英語を使う機会が無くなり、簡単な会話も不安になり、Brush upのつもりで挑戦中。
学ぶ箏に年齢差別はありません。
始めは皆んな一年生。
知る者は学ぶ者にしかず、学ぶ者は愉しむ者にしかず。
記憶が少しずつ蘇りました。
問題は話せても聞こえない箏。難聴です。
聴く、話す、視覚的理解。
できる範囲から愉しみながらやってます。

花森安治
★2017.04.09 重複なしのあらゆる角度から花森安治・『暮しの手帖』が浮き彫りにされたような、抜群の読み応えがあった。中でも椹木野衣さんの「たたかえ暮しの"手"帖」は、じーんと感動に浸ってしまった。生活に欠かせない便利な家電。しかし、家電によって日本人が捨てたものとは?それは、手仕事中心の暮しと心。衣食住の根底にあったのは、身を削って、自分の手によって生活をつくり出すこと。そこに日本人の生の真実があったのかもしれない。物であふれ、自分の手でつくる必要がない現代。もし今、花森安治さんが生きていたら、何を思うだろうか?嘆きや怒りが聞こえてきそうだ。
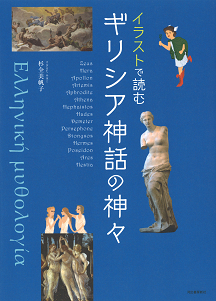
イラストで読む ギリシア神話の神々
杉全 美帆子 著
★2017.04.05 とても楽しく読ませて頂きました! イラストはギリシア神や英雄特徴がうまく表現されていて、可愛らしく親しみやすく、複雑なギリシア神話内の関係が、これまでの本よりもわかりやすく伝わってきました。大変なご苦労だったかと思いますが、本当に良くおまとめになられたと思います(^-^)
エピソードも有名なところを抑えておられて、表記がギリシア名で統一されているのも良かったです。恐らくは、作者様が省かれたエピソードも多々あるかと思います。個人的には第2弾も読んでみたい思いに駆られます。
有難うございました。
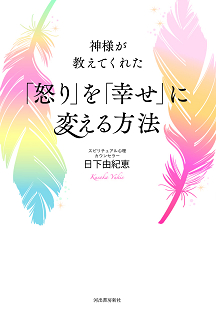
神様が教えてくれた 「怒り」を「幸せ」に変える方法
日下 由紀恵 著
★2017.04.03 この本をいつも持ち歩きたいので、小型サイズの、「文庫化」を切に希望します!!!
それほど、具体的で、価値のある内容でした。
ひとりひとりが、自分の怒りを、このような方法で自己コントロール出来るようになれば、世の中に好ましい変化が訪れる、それほどの大きさを持った 本でした。
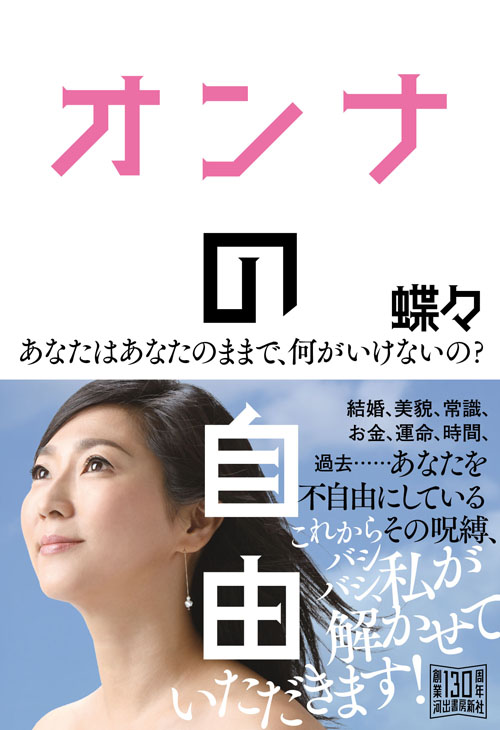
オンナの自由
蝶々 著
★2017.04.02 蝶々様の愛に溢れた文章が
私の呪縛されきった心や魂に
深く染み入って
涙を抑えることができませんでした
今の日本女性が
この本を読んで意識を変えてくれたら
未来は良きに変わるのでは
担当の千様が導いて
蝶々様から生まれたこの本
本当にたくさんの方の手に届くことを
祈っております
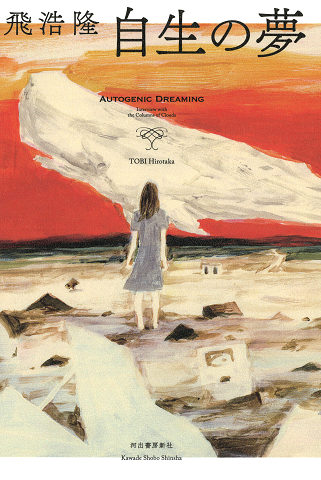
自生の夢
飛 浩隆 著
★2017.03.21 飛作品は初めて拝読しましたが緻密かつ想像力溢れる世界に時間も忘れ読み耽りました。
表題作は故伊藤計劃氏の「読まれるためのテキスト」という考え方が色濃く表れ、結構にやにやしつつかつ、楽しませていただきました。個人的には「はるかな響き」が好きです。
SFでありながら幻想味に満たされたガジェットを用いる辺り(まだ読んでいませんが、)現代のブラッドベリといってもよいのではないでしょうか
あまりの想像力に3割方理解できませんでしたが、だからこそ「現代SFの最高峰」というも言い過ぎではないかもしれません。というよりSFジャンルにおける河出書房新社の代表作でも良いかもしれません
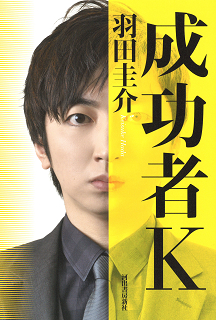
成功者K
羽田 圭介 著
★2017.03.21 噂通り、ページをめくる手が止まらなかったです。
成功者と成り上がりは全く別のものだけどちょっと似ていて、
人間は欲にまみれるっていう落とし穴があるからこそ簡単ではない面白さがあるんですね。
思いがけず、泣ける感じのところもあって満足度高いです。
本書以外でも、羽田作品って結構はまりまね、等身大なのがいいのかな。
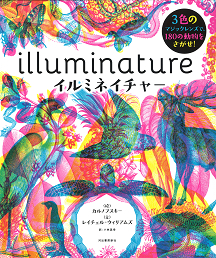
イルミネイチャー
カルノフスキー 絵 レイチェル・ウィリアムズ 文 小林 美幸 訳
★2017.03.19 マジックレンズで本を眺めた瞬間、とてもわくわくしました。子どもと一緒に図書館へ行き、たくさんの本を見たり借りたりしましたが、こんなにわくわくした本ははじめてです!!購入し、手元において楽しみたいと思います。兄弟、親子で同時に一緒に楽しめるように、マジックレンズのみ別売りで購入できるとなお嬉しいです!マジックレンズのみの販売検討をよろしくおねがいします。

大人の塗り絵クラブ
河出書房新社編集部 編
★2017.03.17 初めて、やさしい大人の塗り絵を購入して風景に色鉛筆で挑戦しようかと
書きやすくて、風景もやさしい景色でとても癒やされます。
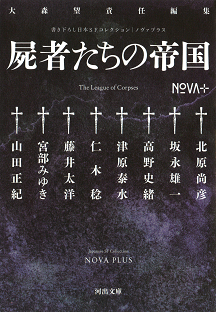
NOVA+ 屍者たちの帝国
大森 望 編
★2017.03.15 まず、一番感心したのがまったくノーマークだった坂永雄一「ジャングルの物語、その他の物語」だ。これはキプリングの「ジャングル・ブック」に材をとり(しかし物語中では「ジャングル・ブック」の存在は認められていない)、そこにもう一つの有名な作品を有機的に絡めることによって、忘れがたいノスタルジーと不穏の入り混じった素敵な作品に仕上げている。驚いたのが高野史緒「小ねずみと童貞と復活した女」。こちらはドストエフスキーの「白痴」が舞台となっているが、それがとんでもない展開をみせる。だって、あのSF作品とあのSF作品とあのSF作品が物語を浸食してきて、もうなんでもありな物語になっているのだ。これはある意味小気味いいね。津原泰水「エリス、聞えるか?」と山田正紀「石に漱ぎて滅びなば」はそれぞれ森鴎外と夏目漱石が主人公となっている。これは示し合せたわけでなく、偶然だったそうな。
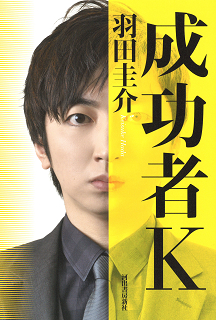
成功者K
羽田 圭介 著
★2017.03.12 [成功者K]を読み終わって、心に残ったのは、分からない!でした。何がどうなっているのか、夜中の1時に頭をかかえました。そのくらい私にとっては衝撃の連続で、今も読み返しています。

自由にいこう! 男着物
鴨志田 直樹 著
★2017.03.05 出版当初にこの本を参考にして着物デビューをしました。中身が非常にまとまっていて、ともすればハードルの高い着物の世界への案内書としては、これを越える本は当時も今も出会えておりません。
男着物の指南書として、この本はよくできております。現況を見ますに、指南書を求める人多くとも、それを満たす本が世に出ておりません。現在世に出ている男着物の本のほとんどが、「お金を持っていること、可処分所得が潤沢な人」を前提として書かれているため、今着物を始めようとしている男性の需要に合致しておりません。
この本は、まさに需要と合致しています。
長文切々と書き連ねましたが、私の想いは上記のとおりです。どうか、増刷をされることを検討ください。
そして最後に、この本を世に出してくださったことに、心から感謝申し上げます。